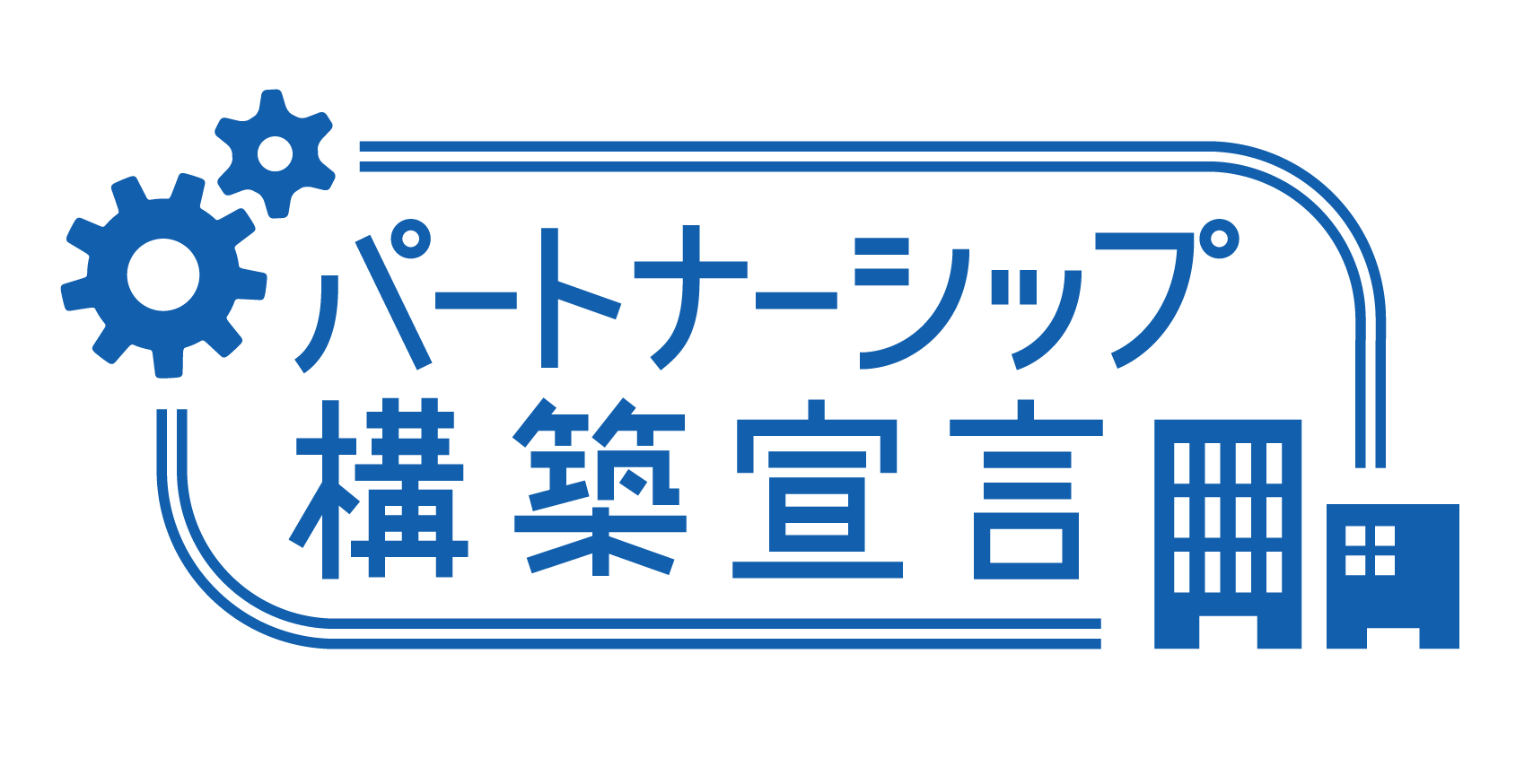[ 2013.10.28. ]
195号-2013.10.25
 企業の人材育成も「ネガティブ:否定」から「ポジティブ:肯定」に重点が移っている。外食大手サイゼリヤは2012年3月、相手の長所を誉め合うグループ研修を取り入れた。社員同士のお互いの良さを認め、ささいな行き違いやトラブルを避けるのが狙いだ。実際、アルバイトの離職が減るなどの効果が出ている。
企業の人材育成も「ネガティブ:否定」から「ポジティブ:肯定」に重点が移っている。外食大手サイゼリヤは2012年3月、相手の長所を誉め合うグループ研修を取り入れた。社員同士のお互いの良さを認め、ささいな行き違いやトラブルを避けるのが狙いだ。実際、アルバイトの離職が減るなどの効果が出ている。
褒めるのにとどまらず、仕事でのミスを表彰するユニークな企業もある。機械部品製造の太陽パーツ(堺市)はチャレンジ精神を育むため、半年に一度、新しいことに取り組んで失敗した社員に「大失敗賞」の賞状と賞金2万円を贈っている。2012年11月に同賞を受賞した営業職の20代男性の場合、新規顧客から受注したものの、納期が遅れるなどして利益を出せなかった事が受賞の理由だった。彼は失敗の教訓を生かし、次に新規受注した時には、利益をしっかり出したという。
『読売新聞2013.3.10』米国の著述家、デール・カーネギーはロングセラー「人を動かす」の中で、人に注意する場合は「まず誉める」のが大事で、その後「遠回しに注意を与える」べきだと説いている。誉めることはやる気を引き出すだけでなく、相手の指示を受け入れやすくする上で不可欠というわけだ。大体以上のような事が人材育成上、「やさしい企業」が最近の風潮になっている。社員を褒めない企業は社員の育成を放棄している企業だとみられ、早期戦力化の中で「叱り飛ばそう」「叱咤激励」の古典的手段は「ブラック企業」にも成りかねない。それらの「褒め」企業が注目されるのは、業績が順調でそれなりの利益を出しているからだ。利益を出していない企業は、例え「褒めて」も反対に組織のバンドワゴンができていない事になってしまう。しかし恥を嫌う日本の伝統的価値観が「怒る企業こそ成長企業」だと将来は回帰するかもしれない。
かつて一世を風靡した「エクセレント・カンパニー」や「ビジュアル・カンパニー」に登場した優良会社を思い出すといい。殆どが、その後、破産したりして消滅してしまい、生き残っているのはわずかだ。優良会社の共通項を取り上げていたわけだが、それだけでは経営は万全ではなかったことを証明した。その共通項は、行動の重視、顧客に密着、自主性と企業家精神、基軸事業から離れない等々だが、どれも優良企業だけでなく企業存続条件としては当然の事だった。どれを取っても、如何に日常業務に落とすかにかかっている。超優良企業だったIBMもパソコン部門を中国企業に売却してしまった。優良企業としての共通項はあったが、後付ながら、時代の流れにその対応が遅れた事が指摘されている。
経営学の流れは1960年代の戦略論、80年代のマネージメント論、2000年代のリーダーシップ論になっているが、その点、循環現象とも言える。社員をどう組織化するかはマネージメント論であるが、リーダーは部下をどう育成するのか、という点からはリーダーシップ論になる。それらの総合が「戦略論」になる。要するに、組織構築上必須と言われている「褒める」という点も人材活性化、モチベーションアップという点から今は脚光を浴びているに過ぎない。
コンサルタント業の飯の種は、人材に焦点を合わせれば、いつの時代も尽きない。新手の切り口で焼き直せば何時でも使えるからだ。だから造語を作ったり、横文字やカタカナが氾濫する事になる。更に精神的医学的立場や生態学からの理由がつけられると反論ができなくなる。しかし「褒める」事が本当に必要なのだろうか? 怒られる事で委縮し、その社員のパーフォマンスは削がれたのだろうか? 山本五十六の言葉で有名な「人はやって見せて、褒めてやらねば、人は動かず」があるが、それは何故なのだろう。海軍は、休日返上で猛訓練に明け暮れた。戦時中には、勤務礼賛の意味で 軍歌「月、月、火、水、木、金、金」が流行った。つまり休みはないくらい軍隊の近代化にまい進していた。常に団体責任を問われ、落伍者がいればそのチームの連帯責任になり制裁も全員だった。
軍隊という特殊な世界だが、そういう中でこそ「褒める」という事が、相手に感激しその重責を再確認する有効な手段なのだ。しかし、敗戦によりすべてが否定された。振り子が正反対に動いたのだ。ポツダム宣言は「軍事的敗北よりも文化的敗北」を意味したという意見もある。1971年当時ベストセラーになった「甘えの構造」で「日本人は人に甘えて依存しがち」だと分析した。年を追って自由を放縦と錯覚し、権利と義務が表裏一体である事を忘れてきた結果、弱者という強者がはびこった。
以前、子供は早く「一人前」になる事が期待されたし、子供も「一人前」になりたかった。「一人前」は立派に働いて妻子を養っていけるという意味だった。社会は一人前を基本的な構成要因としている。独立自尊の気概にあふれた「一人前」の存在が前提にあって初めて可能となる。「褒める」から成長するわけではない、しっかりとした職業観、人生観があれば、一時的な他人からの評価は「移ろいやすい」ものだと自覚している。団塊世代の子育て教育は大いに問題とされなくてはならない。
少子化社会の中で、「怒られた事のない」「何時も大事にされた」子供たちは、いつでも「褒められてきた」し、「褒められることが当たり前に」なっている。これも「結果平等」の帰結でもある。だから、褒める事が必要なのだという議論も成り立つ。反面、褒められてきたから、怒られることも又、効果的なのではないか。精神的弱さを持っているから、それに耐えられないという議論もあるかもしれない。競争社会では「落ちこぼれ」は必然的に発生する。「落ちこぼれ」にも分相応の居場所がある。能力や経験に応じた居場所には夫々達成感、充足感を与えればよい。常に同一の価値観、判断基準しか認めないから自虐的になる。ゴールも様々だと認める必要がある。
我々サービス業は「お客様の立場でものを考え、行動する必要がある」、お客様に喜ばれれば褒め、クレームが出れば叱責しなければいけない。一般的には「褒める 30%、叱る、怒る、注意 70%」だといわれる。勿論その比率を何時も把握している必要がある。そうでないと片手落ちで反感を買う。前の立場からは、その褒め方も「全員の前でするな」とか、「個人的に行え」とか言われ、叱り方も同じ様にしなくてはいけない事になる。しかし、つい数十年前は全て全員の前が原則だった。
最近、怒るのは悪いが、叱るのは良いという。感情的だとか理性的だとか、相手が納得しやすいとか、様々に言われるが、机上の話ではなく実務で使い分ける事ができるか大いに疑問だ。
実務では通常、注意するのが普通で、注意しても聞き分けないから、「怒る、叱る」が出てくるのである。「怒る、叱る」は、そもそも、その上司が日常業務上での基本的動作を怠っているからである。それは「ほう・れん・そう:報告、連絡、相談」を待っているからだ。
部下や後輩から待っているのではなく、上司や先輩が自ら出かけ、聞き、点検し、指示しなくてはならない。待っているから、事案に即応できないのであって、初期の予定通り結果が出ないからと言って、その失敗をあげつらったり、怒ったり叱ったりすることは、上司の無能を表している。
小さな成功体験を経験させたりするのも、形を変えた「褒める事」だし、モチベーションも向上する。「褒め殺し」という言葉もあったが、「叱り殺し、怒り殺し」はない。自ら手を下さない「褒め殺し」こそ、禁じ手ではないか。皆がいい子になりたがる現代の風潮でこそ起きる手段だろう。
要は「褒める、叱る、怒る」は組織掌握上の手段で適宜に行えば良い。そして、個人に限定するか、連帯責任にするかは人類数千年の歴史も混迷し正解がない。人を掌握する王道は一つではない。
(社長 三戸部啓之)