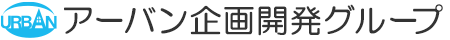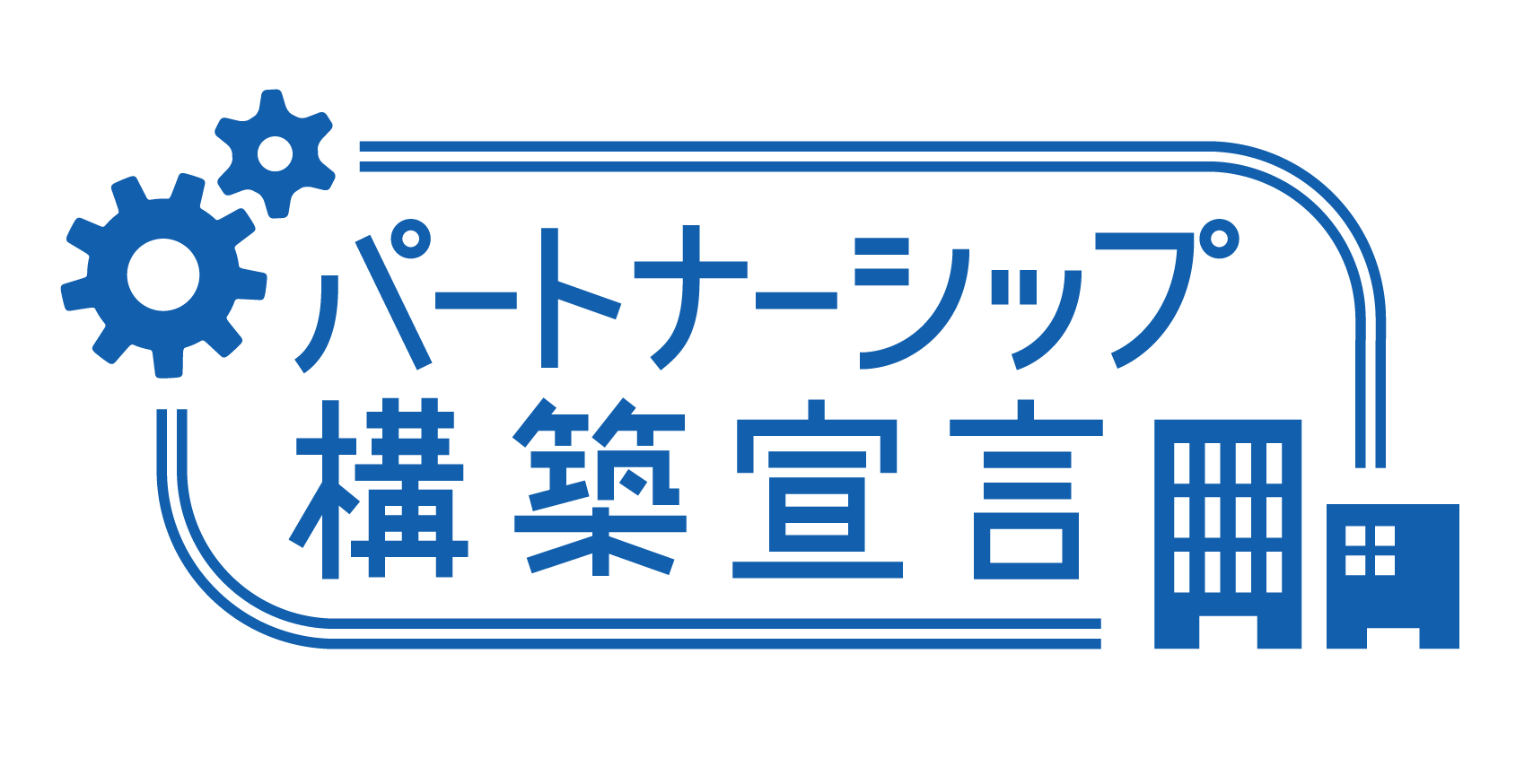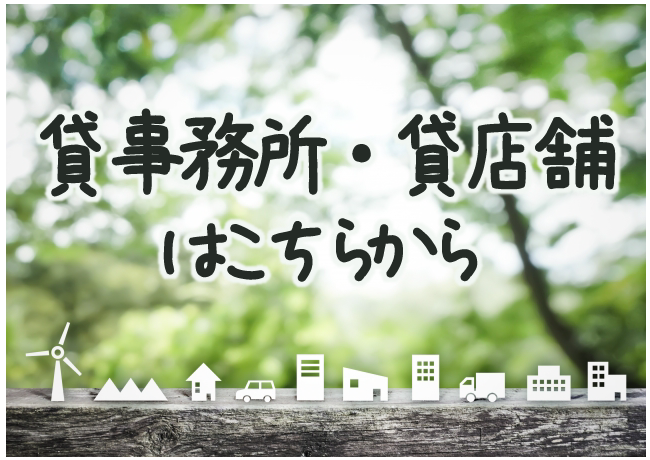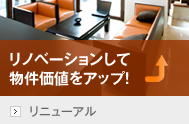[ 2025.5.1. ]
332号-2025.5
 慶應義塾大学の創始者である福沢諭吉は明治15年に「時事新報」という新聞を創刊した。同紙は、政党色のない、独立不偏を編集方針としていた。彼は、時事新報の紙面充実と部数拡大に力を入れつつ、「広告の効果」「媒体としての新聞の価値」を繰り返し力説した。実際、彼は、新聞広告を集めるための広告主向け広告にも積極的で、「日本一の時事新報に広告するものは、日本一の商売上手である」と刷ったビラを風船で飛ばしたこともあった。彼は明治16年、時事新報の社説に「商人に告るの文」を書いている。この社説で展開されているのは、『商いは広告をすべき』という彼なりの「広告論」で、いささか説教的な「自社広告」という側面があるが、彼の広告論はビジネスの本質を突いている。社説を要約すると以下のようになる。
慶應義塾大学の創始者である福沢諭吉は明治15年に「時事新報」という新聞を創刊した。同紙は、政党色のない、独立不偏を編集方針としていた。彼は、時事新報の紙面充実と部数拡大に力を入れつつ、「広告の効果」「媒体としての新聞の価値」を繰り返し力説した。実際、彼は、新聞広告を集めるための広告主向け広告にも積極的で、「日本一の時事新報に広告するものは、日本一の商売上手である」と刷ったビラを風船で飛ばしたこともあった。彼は明治16年、時事新報の社説に「商人に告るの文」を書いている。この社説で展開されているのは、『商いは広告をすべき』という彼なりの「広告論」で、いささか説教的な「自社広告」という側面があるが、彼の広告論はビジネスの本質を突いている。社説を要約すると以下のようになる。
1.商売繁盛は、「正直」「熟練」「廉価」で客に対応すべきである
2.それを知らせる工夫をしなければ商売繁盛はありえない
3.商いは「人に知られること」が最も大切である
4.人に知られる方法は、まず人通りの多いところに店を開くこと
5.店頭に看板を掲げ、店を飾り、人目につくよう品物を並べ、注意を喚起すべきである
6.人通りの多い場所にポスターを掲げ、さまざまなチラシを配布しなければならない
7.商いには「広告するに適当なチャンス」がある。その機会を見極めるのが肝要である
8.広告文は素人では書けない、有名な筆者に依頼すべきと信じている人が多いが、それはとんでもない間違いだ
9.世の中に手紙が書けない人はいないはず。手紙で自分の意志が通じる人が、広告文を書いて自分の意志ができないはずがない
どうだろう。今に通じる広告論に違いない。
福沢諭吉が現れるまで、新聞の収益源は「購読料」や「折込チラシ」がメインだったらしい。
しかし、福沢諭吉はその常識を覆す新しい収益化の方法を生み出した。
その方法が、「新聞広告」だったというわけだ。
誰もがビジネスで感じているように、新しいものを売り出すのは簡単なことではない。商売繁盛は、「正直」「熟練」「廉価」で客に対応すべきであるが、同じ仕事をしていても、売上に差がつくことは少ない。どこで売上に差がつくかというと世の中に知られているかどうか!だ。マスセールスの時代には正論だ。だから商いは「人に知られること」が最も大切になる。しかしながら世の中に知られることは非常に難しい。人通りの多いところに店を作り、看板を掲げ店を綺麗にし、チラシを配り張り紙を出すことが大切だと言われている。しかも昭和の時代も今も最も効果が高いのは新聞広告であった。新聞広告は老若男女が読む。しかも自分でお金を払って読んでいるのだから買った人は隅から隅まで読む。チラシを全部読んでもらおうとすると非常に時間と手間がかかるから、キャッチコピーで判断されてしまう。新聞1部とチラシ1枚では、同じ数に見えて成果が全く違う。汎用品や比較的廉価な物品はチラシ広告、高額な物品やキチンとした説明が必要な物品は新聞広告と住み分けられている。広告を出すタイミングも難しいが広告は毎日出した方が良い。なぜなら、広告というのは最近は1日2日で忘れられてしまうからだ。
また広告は腕のある人に書いてもらった方が良いと言われているが、それは違う。
自分の気持ちのこもった文章が書ければ、その気持ちは相手に伝わる。
多少のミスがあっても意味がわからないことはない。
海外では”商売の秘訣は広告にあり”と言われており企業は広告に多額のお金をかけている。
競合と同じような宣伝しかやっていないなら抜きん出ることはできない。
競合はチラシしかしていない!だったら今がチャンスといえる。福沢は宣伝しなければ競合に勝つことはできないという広告宣伝の重要さを訴えつつ反論を上手に押さえている。
例えば
反論1:チラシを出している→チラシより新聞の方が読んでもらえる
反論2:いつ出せばいいのか(今でなくてもいいのでは?)→毎日出すことが重要。海外でもそう。
反論3:広告を依頼するお金がない→自分で作れば良い。綺麗な文章より伝わる文章
そして最後に他社より抜きん出たいなら他社がやっていないことをやるべき→今すぐやるべき
と訴えている。
反論処理をしつつ独自の優位性を上手く打ち出す!。
これは、現代においても非常に重要な宣伝の要素だ。しかし、今の時代多くの企業が広告を出し消費者は広告に慣れてしまった。
つまり単に広告を出しても顧客は見ない、読まない、信じない、という困った事実がある。
今、効果的に宣伝するためにはターゲットにド直球で刺さる打ち出しを行う必要がある。
ターゲットにド直球で刺さる打ち出しをする為には、顧客の興味・関心を推測して、ターゲットを絞り込んで広告配信するしかない。例えば、ダイエットサプリを調べているユーザーをダイエットに興味・関心あるとみなして広告を配信するリステニング広告の一種だ。
最近ではAISAS(アイサス)が提唱されている。2004年に株式会社電通が提唱した購買行動モデルでSNSの普及によって、口コミが購買動向に影響するようになった。
Attention(認知)・・商品・サービスを認識する
Interest(関心)・・商品・サービスに興味をもつ
Search(検索)・・・商品・サービスをインターネットで検索する
Action(行動)・・・商品・サービスを購入する
Share(共有)・・・購入後、ブログやSNSにレビューを書く
従来、広告は企業側(売り手)からの発信だったが、その真意性に疑問を持たれるようになってきた。インターネットの普及により売り手側だけでなく、買い手側からの情報も安易に入手することができるようになった。更に物品が行きわたり飢餓感がなくなると、勢い不要不急の購入動機は減退する。購入欲求を活性化するためには、品質や機能ではなく、感情価値が決定要因になる。つまり持つことの優越感、物語性が必要になった。SNSによりその使用価値や感情価値が拡散されると企業側の広告戦略は変更をせざるを得ない。購買動機付けだけでなく、購入後のアフターセールスも含めたトータルの顧客フォローがないと販売拡大には結びつかない。我々不動産業界でもアフターコロナ禍ではSNS対策が急務になっている。ネット上の口コミが賃貸仲介や管理に影響する。入居希望者はサイトに掲載された物件を閲覧するのは勿論だが、それを扱う仲介業者の対応や表示の仕方に評価コメントを書き、貸主側のオーナーも管理を任せる判断の根拠として、ネット上の書き込みを注視しているからだ。勿論、入居審査でお断りした入居者からの悪意に満ちた口コミもあり、そのまま受けとることはできないが、口コミが判断の主要な要素になっている点は否めない。物件だけでなく社員の対応も商品化されてきた。今後は社員力が企業の差別化要因となる時代である。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之