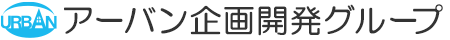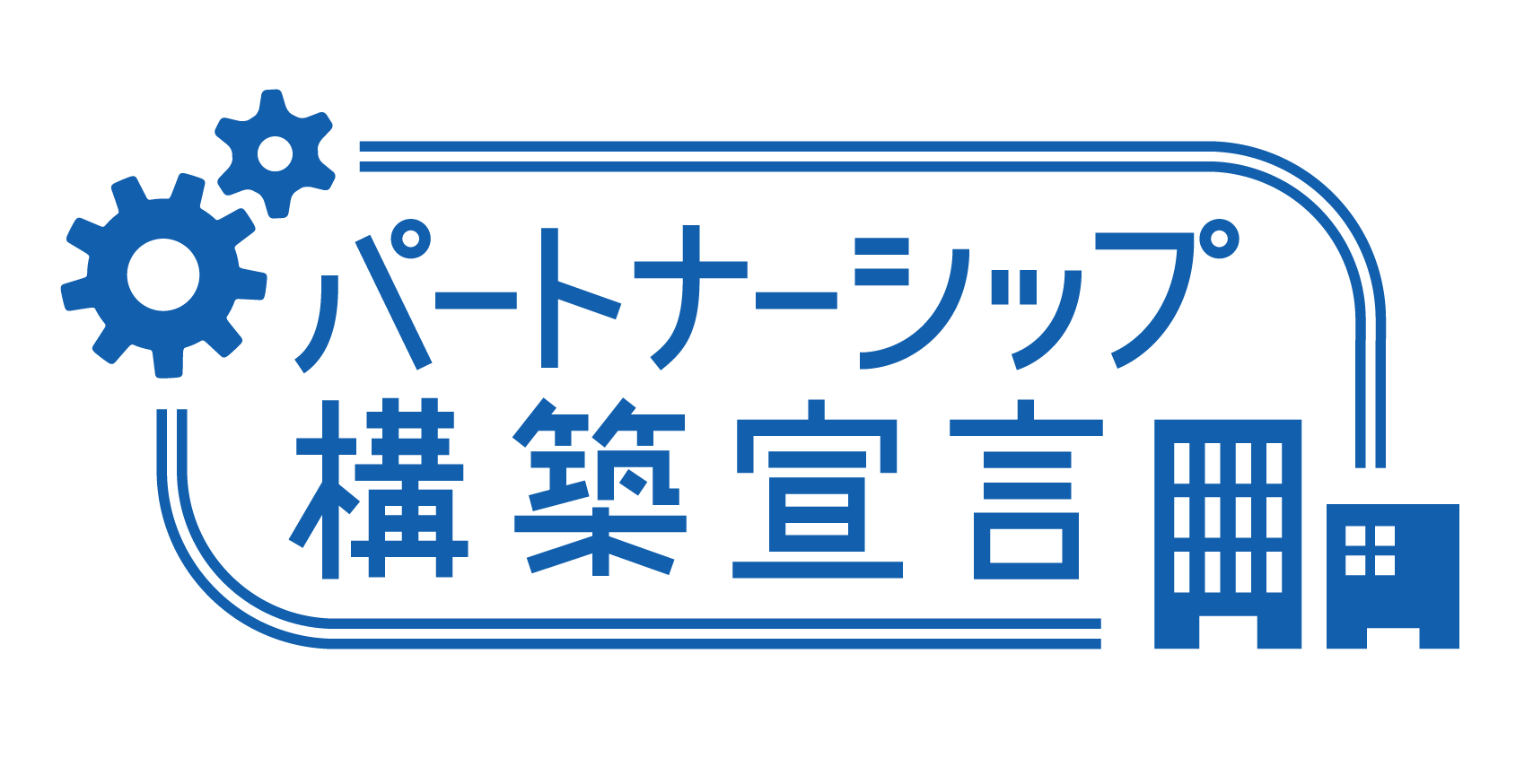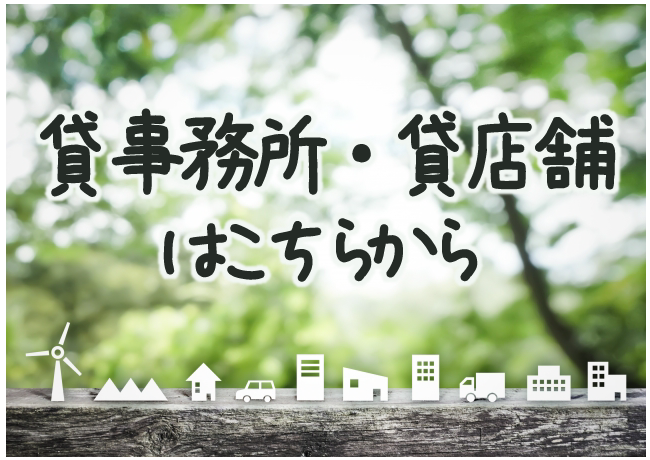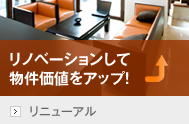[ 2025.11.1. ]
338号-2025.11
 アフターコロナでは営業のやり方が、従来とは劇的に変化したといわれている。対面営業から間接営業になった。直接顧客のところへ行って話をするのではなく、先ずセミナーとかDM、チラシ、マスコミ媒体を使った広告や、SNS等の口コミで反響を取り、ZoomやTeamsで初期のプレゼンテーションをするようになった。顧客側も見知らぬ人の訪問を嫌うようになり、保安上の観点からも避け始めている。相手の時間を恣意的に奪うという点からも問題にされるようになってきた。昔の一軒一軒個別訪問するという「どぶ板営業」は効率性から言っても、社員の精神的な疲弊度から言ってもできなくなっている。更に営業員自身が、3K職場といわれる「汚い、きつい、危険」の労働環境を忌避している為、人材が集まらなくなったこともある。かつて営業が「社内の花形職」と呼ばれた面影は今はない。「企画営業」とか「コンサル営業」とかオブラートに包んでもその実態は変わらない。戦術的に言えば地上戦なのだ。TV・新聞広告は戦略爆撃に相当する。世界最先端の軍隊を持つ米国でも、戦闘の仕方は変わったが、歩兵を主体とした部隊は現存している。その理由は、いかに戦略爆撃やミサイル攻撃をしても、そのエリアを完全に掌握するには歩兵部隊が必要だという事だ。ビジネス戦線でも同じことが言える。地域密着という企業ならばこの地上戦を避けることはできない。いかなる広告媒体を使用しても、知名度を上げることはできるが顧客との人間関係構築は不可能だ。対面でこそ信頼され信用されるのが通常だろう。だから、様々な顧客と接し、会話のやり取りの中でしか、そのスキルは磨かれない。その為の訓練が飛び込み訪問という事だし、机上の空論ではなく実体験に基づく極めて即効性のある教育訓練だ。面談件数の量こそ自分のスキルを磨くことができる。当社でもその件数はKPI(Key Performance Indicatorの略、「重要業績評価指標」と訳される)の要素になっている。
アフターコロナでは営業のやり方が、従来とは劇的に変化したといわれている。対面営業から間接営業になった。直接顧客のところへ行って話をするのではなく、先ずセミナーとかDM、チラシ、マスコミ媒体を使った広告や、SNS等の口コミで反響を取り、ZoomやTeamsで初期のプレゼンテーションをするようになった。顧客側も見知らぬ人の訪問を嫌うようになり、保安上の観点からも避け始めている。相手の時間を恣意的に奪うという点からも問題にされるようになってきた。昔の一軒一軒個別訪問するという「どぶ板営業」は効率性から言っても、社員の精神的な疲弊度から言ってもできなくなっている。更に営業員自身が、3K職場といわれる「汚い、きつい、危険」の労働環境を忌避している為、人材が集まらなくなったこともある。かつて営業が「社内の花形職」と呼ばれた面影は今はない。「企画営業」とか「コンサル営業」とかオブラートに包んでもその実態は変わらない。戦術的に言えば地上戦なのだ。TV・新聞広告は戦略爆撃に相当する。世界最先端の軍隊を持つ米国でも、戦闘の仕方は変わったが、歩兵を主体とした部隊は現存している。その理由は、いかに戦略爆撃やミサイル攻撃をしても、そのエリアを完全に掌握するには歩兵部隊が必要だという事だ。ビジネス戦線でも同じことが言える。地域密着という企業ならばこの地上戦を避けることはできない。いかなる広告媒体を使用しても、知名度を上げることはできるが顧客との人間関係構築は不可能だ。対面でこそ信頼され信用されるのが通常だろう。だから、様々な顧客と接し、会話のやり取りの中でしか、そのスキルは磨かれない。その為の訓練が飛び込み訪問という事だし、机上の空論ではなく実体験に基づく極めて即効性のある教育訓練だ。面談件数の量こそ自分のスキルを磨くことができる。当社でもその件数はKPI(Key Performance Indicatorの略、「重要業績評価指標」と訳される)の要素になっている。
言うまでもなく、飛び込み営業の他に3Kの代表的職場には建設業、土木業、介護士、看護師、警察官が入る。そこでは、肉体労働が基本で休みも少なく、高所や地下での作業などもあり、土や廃材を扱う仕事は汚いというイメージがある。介護士、看護師は死に直面する仕事だ・・近年ではITサービス業界やコンピューター業界などにおいて「きつい」「帰れない」「給料が安い」事を「新3K」と称するなど、時代や業種によって該当する意味は変化している。肉体的、精神的に負担がかかる職業は時代とともに「厳しい職場」と判断されるのだ。最終的にはそれらが「ブラック企業」の烙印を押されることになる。ブラック企業の意味も当初の意味からは相当変化している。職業に貴賤はないが、知識情報社会ではどうしても頭脳労働者が評価され、肉体を酷使する職業は下位にみられ給与を含めた待遇も悪い。同じ稼ぐならラクして稼ぎたいのが一般的風潮だから猫も杓子もこぞって3Kは避けてしまう。そこで政府は3K職場に入る仕事をエッセンシャルワーカーと呼びその重要性を訴えたことがあった。エッセンシャルワーカーは「生活必須職従業者」と呼ばれ、医療や福祉、第一次産業や行政、物流や小売業など、いかなる状況下でも必要とされる社会生活を支える職種と言われる。厚生労働省がエッセンシャルワーカーをコロナ禍の最中に「緊急事態制限時に事業の継続を求められる事業者」と定義し、その重要性を国民に訴えたのは、国側もそれらの職業の不可避な重要性に気が付いたことになる。それに伴い、少子化社会で2050年には移民労働者に頼る方策も、低賃金の日本に魅力を感じてくれるかは心もとない。現在当たり前の社会的サービスが2050年には受けられないことになる。労働生産人口が今より1000万人不足すると予想されているからだ。現在に置き換えると2割の働き手がいなくなることになる。女性の労働戦線復帰や定年延長も焼け石に水だ。現在でも2024年問題として人手不足が懸念されている。
タクシーや運輸関係のトラック運転手が不足して、手持ちのトラックの稼働が50%になっている会社もあるという。公共交通機関のバス便も運転手不足で減便があちこちで起きている。建設工事も人手不足で工期遅延が常態化しているという。それに伴い建築単価も高騰している。人手不足が生活の利便性を徐々になくしていくと同時に、その単価も上がり益々我々の生活を苦しくしていくというスパイラルになっている。更に期待される生産労働年齢にある若者たちが「ラクして稼ぐ」志向を持てば、エッセンシャルワーカーになるのは少なくなる。政府は移民政策に舵を切ったが先進国の例を見ても問題が多い。「ラクして稼ぐ」事が当たり前になると「タイパ」とか「コスパ」重視になってくる。因みに「タイパ」はタイム・パフォーマンスで時間当たりの成果を言うらしい。こういう風潮が当たり前になれば「じっくりと時間をかける仕事」は、バカバカしくて誰も携わらなくなる。当然、「修行」という観念はなくなる。「石の上にも3年」なんて誰も考えない。ホリエモンが以前、Twitter(今のX)で言っていたように、すし職人が一人前になるのに10年かかるといわれるが、YouTubeで見れば1時間でマスターできるという意見も出てくるはずだ。待つ=熟成がない社会は全てが即効性を求める社会になってしまう。一面スピードは必要だが、人類の生活パターンはそれに準じるようには進化していない。モノをじっくり考える事もなくなるし、対話を重視する姿勢もなくなる。
以前は、ある大手上場住宅販売企業も当然に取り入れていた「3000本ノック」と揶揄された、新人の飛び込み訪問も今 や、ブラック企業の要素になっている。我々「昭和営業」を経験したオヤジは、その効果を知っているだけに承服できない。訪問販売では99%が断られる。アフターコロナでは感染予防の関係から、顧客の企業も軒並みに顧客開拓のための訪問はしなくなってきた。間接接触が基本となっている。DMや電話によるアポイントによる訪問や、セミナーを主体とした顧客開拓に代わってきた。それなりの効果は認められるが、飛込みによる応酬話法は鍛えられない。つまり断りに対する切り返しができない。会話のやり取りの中で顧客の真意や潜在欲求の引き出しができない。営業に必要な顧客の潜在心理の把握というポイントは、顧客との会話のやり取りの中からしか生まれない。そういうスキルがないと顧客の表面的な言辞で判断してしまい、かえって顧客の意図しない方向へ行ってしまう事も多い。結果的に顧客との信頼関係も生まれない。顧客とのトラブルでも事実関係をきちんと整理せず、場の雰囲気や相手の一方的な論駁(ろんばく)にさらされてしまう事も多くなる。
や、ブラック企業の要素になっている。我々「昭和営業」を経験したオヤジは、その効果を知っているだけに承服できない。訪問販売では99%が断られる。アフターコロナでは感染予防の関係から、顧客の企業も軒並みに顧客開拓のための訪問はしなくなってきた。間接接触が基本となっている。DMや電話によるアポイントによる訪問や、セミナーを主体とした顧客開拓に代わってきた。それなりの効果は認められるが、飛込みによる応酬話法は鍛えられない。つまり断りに対する切り返しができない。会話のやり取りの中で顧客の真意や潜在欲求の引き出しができない。営業に必要な顧客の潜在心理の把握というポイントは、顧客との会話のやり取りの中からしか生まれない。そういうスキルがないと顧客の表面的な言辞で判断してしまい、かえって顧客の意図しない方向へ行ってしまう事も多い。結果的に顧客との信頼関係も生まれない。顧客とのトラブルでも事実関係をきちんと整理せず、場の雰囲気や相手の一方的な論駁(ろんばく)にさらされてしまう事も多くなる。
最近、カスハラというモンスタークレーマーが大きな問題としてマスコミなどで取り上げられているが、「お客様は神様です!」という昭和の感覚も従業員ファーストの中で見直されてきた。相撲でいえば一方的に土俵際に押しまくられる初心(うぶ)な社員が多くなってきた。クレーム処理に「タイパ」はないはずだが、「踏ん張る、粘る」という訓練がされていないから当然だといえる。当社でもそういう社員が増えてきており、今後の主要改善課題だが、すぐ金銭的解決にもっていこうとする社員が増えている。妥協点を探るというのが交渉であるはずだが、そういう精神的負荷のかかる事態を故意に避けているのが最近顕著にみられるのには一抹の不安がある。クレーム対応から新たな信頼関係が生まれるという昭和の教育も絶えてきたのは悲しい現実だ。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之