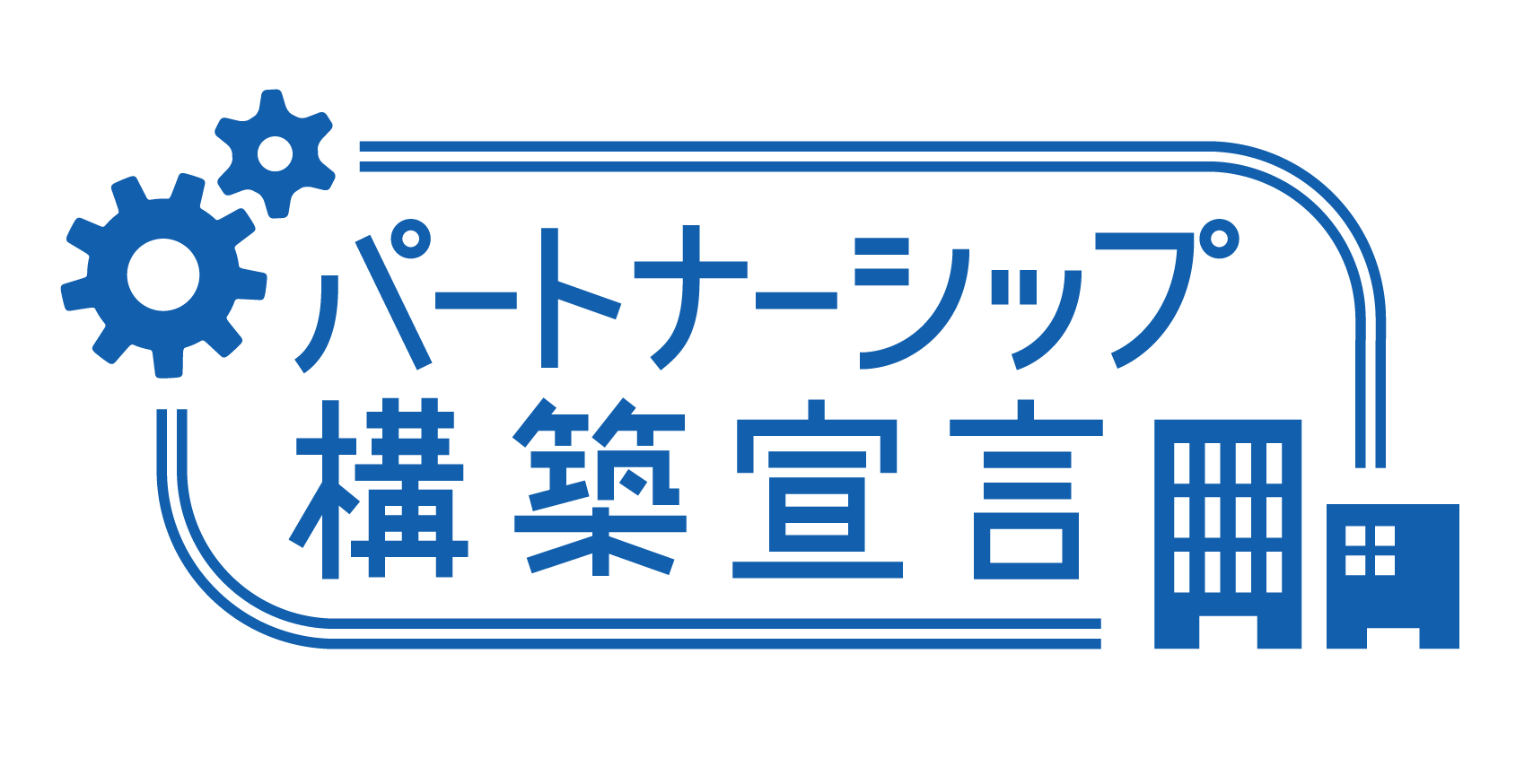[ 2021.12.1. ]
293号-2021.12
最近、国力の低下を憂いて国の内外から「日本人論」が人口に膾炙されている。
「対話ができず、不用意な笑いをする不気味さ」と「男女差別」が根強い事だ。
「日本人は、会話は好きだけど対話は苦手」だと一般に言われている。会話とは一般的に「気の合った人たちの間で行う話し合い」をいい、対話とは「必ずしも気の合うとは限らない人たちの間で行う話し合い」を言う。人が複数いれば、それぞれ考え方も感じ方も異なる。日本のような同種同族の国民の中では対話は必要ではなかった。長老や慣習でコトの判断ができたからだ。欧米のような異種異族の社会ではお互いの話し合いで決めることが必要だ。意思が統一されないと行動ができないからだ。その為、小学校から自分の意見を述べ、他人との違いを踏まえ「合意形成努力」という訓練がされている。しかし、日本では「協調性」が重視され、異端な意見はことごとく排斥されるから、対話の訓練ができない。「阿吽の呼吸」や「その場の空気」が支配される。そのDNAを持つ農耕村社会の中では「序と和を乱さない」事が、村落共同体を維持する不可欠な要素なのだ。多様性を活かすという観点では、違う考えや意見を持つ人たちが対話を通して、新たな価値を生み出すことに意義がある。けれども、「一対」の「対:つい」という意味もあるのだが、対話の中に対決の「対:たい」が入っているためなのか、『自分が正しいことを主張し続ける』『自分とは異なる意見を真っ向から否定する』『相手の考え方の矛盾をついてやり込めるのが対話だと考えている』人がいる。
特に最近はネットによる悪影響もあって、自分と異なる意見を徹底的に批判する傾向が強まっている。誰しも「自分はこれが正しい」と思っていることを否定されると良い気はしない。特にその否定が、理屈が通っているならまだしも、論点をすり替えて否定する主張であったり、権力を傘にした一方的な物言いだったりすると猶更だ。
欧米諸国との決定的違いは、欧米では「何を言ったのかに是非を問う」のに、日本では「誰が何を言ったのか」が決め手になる事だ。会社では、社内の上下関係があるため「上司-部下」の間で話し合う際には、ざっくばらんに意見を戦わせて、新しいコンセプトを見つけるというよりは、上司が一応部下の意見を踏まえて、既定路線に沿ってコンセプトをまとめることになりがちだ。対話がきちんと成立するには、その話し合いに参加する人たちの間で、たとえ自分と意見が違っても、その意見を一つの意見として尊重するというのが前提条件になる。一方、多くの日本人は「親や先生の言うことはちゃんと聞きなさい」「周りの人たちとは仲良くしなさい」と躾られているので、皆が反対する中で、自分の意見を堂々と述べることは苦手な人が多い。今や何が正しいかを判断するのは難しくなっている。「LGBT」が認知されようとしている中で、ディズニーランドが早くも“Ladies and Gentlemen, Boys and Girls”と呼びかけるのを止める旨、報道されていた。そこに差別的な意図はないにせよ、差別と捉えかねないという懸念から防御策として呼びかける言葉を変えるらしい。
しかしながら、発信する側に意図がなくても、知らないうちに相手を傷つけていることはある。その際、大切なのは「発信する側がきちんと説明をつくすこと」「受信する側も相手の意図に思いを馳せる」ことだ。意見や考えが違うのは当たり前だ。違うことで相手を非難する資格はないし、違うことでむやみに悩む必要もない。異なることを前提に、それぞれが1人の人間として自分の考えや意見に磨きをかける事が必要だ。対話はそのためにある。対話の目的は相手の意見を打ち負かすことでなく、自分の意見に磨きをかけることにある。ダイバーシティーが言われて久しいが、定着しない理由がそこにある。
反面、欧米では「力の論理」が支配する。話し合いがつかなければ統一を図るために「相手を抹殺」する必要がある。現代の日本人にはなかなか理解できない「民族浄化」「ジュノサイド」が起こりやすい。何かのきっかけで異種に対して排斥行動が起こる事もある。
対話だけでなく男女平等に関しても、人の意見は様々だが、少なくとも、日本では女性の力を会社の業績アップに上手く活かし切れていないことが多い。これは国際的にも様々な観点から言われている。
そもそも、勤労観は宗教や政治経済環境に依拠する。初期高度成長期には、ILO(国際労働機関)調査で世界の管理職に占める女性の割合は27.1%だが、日本は12%と主要7カ国(G7)で最下位だ。役員に占める女性の割合はG7ではフランスが37%とトップで、平均では約23%。日本は3.4%に過ぎない。国連が定めた「国際女性デー」に合わせて運動が活発になっている。能力があるのに不当に差別されているという訳だ。かつての「ウサギ小屋」批判と同じ構図だ。前回は貿易摩擦が背景にあったが、今回はジェンダーギャップからの人権尊重がある。
人権尊重は民主主義国家では世界的な風潮だが、根底にあるのは労働生産性のアップとGDPのかさ上げだ。世帯所得を上げることによる消費購買行動の増加だ。女性の自立を促すことにより従来の儒教思想も払しょくされる。以前は職住近接が当たり前で働く場と住む処が一緒だったが、後期高度成長期になると労働生産性を上げるために職場と住まいを分け居住性を重視するようになった。所謂、田園都市構想だ。
鉄道を延伸し環境の良い場に住まいを設け、新たな労働活力を維持させた。そこでは必然的に労働単位としての核家族が必要となり、夫婦子供2人の標準家庭が理想とされた。妻は夫の労働生産性を担い家事と子供の教育を担当した。だから専業主婦というカテゴリーが政策的に必要だったし、主婦の労働はあくまでも夫の補佐的な役割で、夫の収入の補助と の位置づけだった。だから内職と言われていたし労働単価も著しく安価だった。妻の自立はかえって家庭の存続を危うくするもので、毎月の給与は夫から恭しくいただくものだった。妻の消費にも一々夫が口を出したし子供の教育まで妻の責任になり、極めて従属的家内労働が当たり前だった。経済的な紐帯はもとより、「子は鎹」と夫婦間の精神的縛りもあり、妻の不満は社会的に黙殺された。だから離婚はご法度で、今ではよく言う「バツイチ」なる言葉は当時「我慢ができないわがままな人」と烙印が押されたし、妻の不倫による刑法上の姦通罪も廃止されたのはGHQの指示による1947年だ。
の位置づけだった。だから内職と言われていたし労働単価も著しく安価だった。妻の自立はかえって家庭の存続を危うくするもので、毎月の給与は夫から恭しくいただくものだった。妻の消費にも一々夫が口を出したし子供の教育まで妻の責任になり、極めて従属的家内労働が当たり前だった。経済的な紐帯はもとより、「子は鎹」と夫婦間の精神的縛りもあり、妻の不満は社会的に黙殺された。だから離婚はご法度で、今ではよく言う「バツイチ」なる言葉は当時「我慢ができないわがままな人」と烙印が押されたし、妻の不倫による刑法上の姦通罪も廃止されたのはGHQの指示による1947年だ。
そこから約40年後、少子化を踏まえた「男女雇用機会均等法」が1986年施行され「総合職・一般職」の職能区分が現れたが、その後35年近く経過しても中々定着しなかった。2015年女性活躍推進法で指導的立場にある女性割合を30%にするよう企画されたが、男性の育児に対する関与を今まで以上にさせなければ女性の社会進出は制約される点から、2021年「育児休業法」が改正され、男性の休業取得促進が図られた。機械化、IT化が図られたことで男女の労働価値の差がなくなった事が背景にあるからだ。まさに令和の「総動員体制」だ。成人年齢を18歳に引き下げ、定年を70歳まで引き上げ労働生産人口の拡大を図った。アフターコロナで、折しも「ガラパゴス経済の転機」が現れた。世界的なインフレ懸念が浮上する中、日本は消費者物価がほとんど上がらない。モノもサービスも、賃金も安くなったニッポンは物価上昇の波に向き合えるかが、真剣に考える時期に来た。
米ネットフリックス、アマゾンは米国の1.6倍の値上げに踏み切った。木材や主要な産業資材価格も海外のほうが1~2割高い逆転現象が起き、欲しい量を十分確保できない事態に陥った。購買力平価ベースで比べると日本は米国の58.7%に過ぎない。賃金の上がらないニッポンの負担は重くなってきた。企業は製品に価格転嫁できない。その結果、消費も伸び悩み企業収益も低迷する悪循環が続いている。製品の付加価値を高めて値上げし、賃上げにつなげるグローバル企業。この常識が通用しない日本にインフレの波が押し寄せてきたといえる。このままでは日本人の好きな「マグロのトロ」もめったに食べられなくなる。中国人や東南アジアの人々の爆買いを、観光立国の下に諸手を挙げて喜んだ為政者の「ノー天気な」感覚はいただけない。低成長、低インフレ、低金利。この病理の怖さは痛みを感じにくい点にあり、間違いなく「プア中間層」が増えつつある。所得を製品価格に転嫁できないとすれば、労働人口を増やし世帯当たりの所得を増やすしかない。それが共稼ぎ世帯の増加となったが、それを所与として認知する為には男女平等が必須になる。第4の黒船の到来で、ニッポンの経済社会構造はコロナ禍と合わせ「K字経済」の激変は逃れない。対話を重視した働き方改革だけでなく、我が不動産業界も女性の活用ができなければ淘汰が進むのは間違いがない。
会長 三戸部 啓之