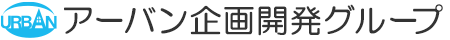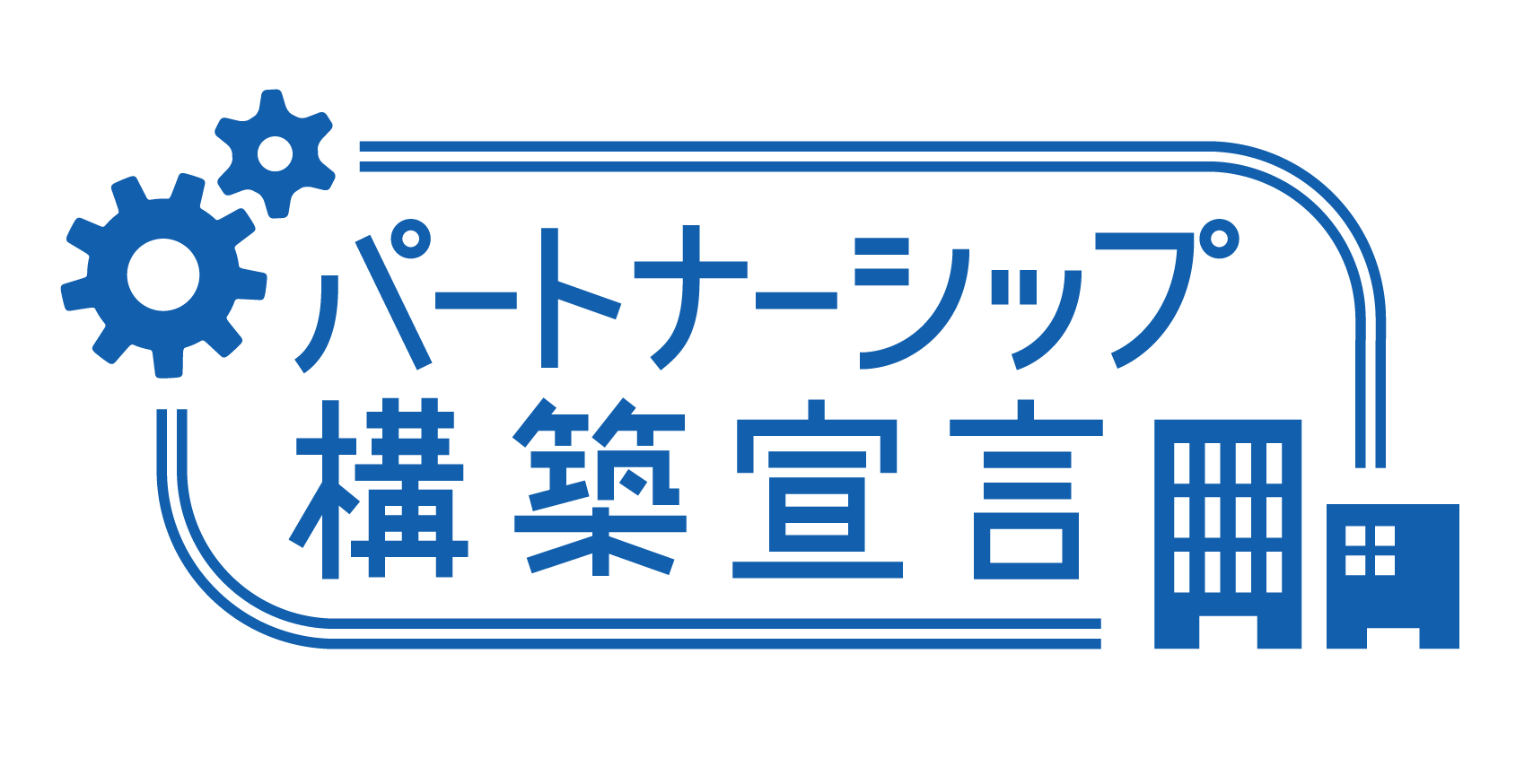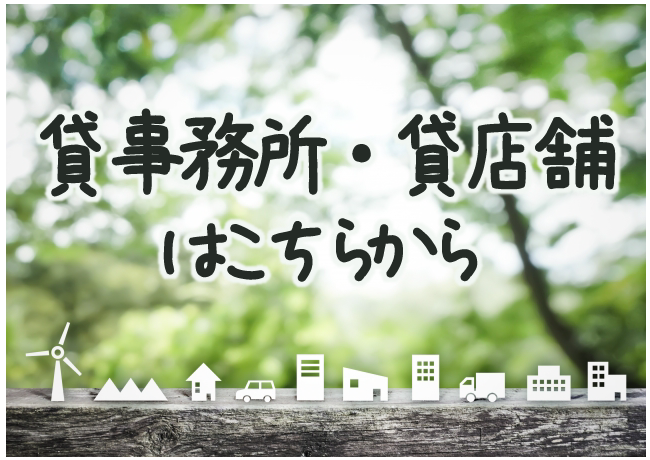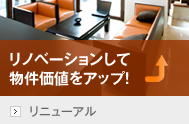[ 2025.7.1. ]
334号-2025.7
今月号は経営コンサルタントの岩井徹郎先生の承諾を得て、メルマガの内容を転載しています。

◆◆◆『会社組織の中では「ミス=減点」「ミス=評価ダウン」という構造が根強くあります。
だからこそ、多くの人が失敗を過度に恐れたり、自分のミスに蓋をしたりする傾向にあるのもまた事実です。
独立して経営者になった今、はっきりと感じるのは、ミスに対する向き合い方が経営者としての成長スピードを左右するということ。
経営においては、ミスをゼロにすることは不可能です。むしろ重要なのは、ミスからどれだけ学び、再発を防ぐ仕組みを自分で考えられるかどうかです。「自責」という言葉には、「自分を責める」というニュアンスが強いかもしれませんが、私が考える自責とは「自分にできることは何だったかを問い直す力」です。
決して自分を責めて落ち込むことではなく、課題を他人のせいにせず、自分の手で改善策をつかみにいく態度なのです。
たとえば、ゴルフをされる方であれば「シャンク」というミスショットをご存知でしょう。
原因はスイング軌道、姿勢、重心の取り方など、実にさまざま。しかしプロはこのミスを単なる事故とは捉えません。
原因を特定し、修正する手段を試し、再発を防ぐチェックリストを頭に入れているのです。
経営もこれと同じです。
ある社長さんは、社員との意思疎通のズレからトラブルが続出していました。
最初は「部下が指示を理解しない」「やる気が足りない」と嘆いておられましたが、深掘りすると、ご自身の指示が感情に左
右されていたり、曖昧な言葉で伝えていたりしたことが見えてきたのです。そこで、「自分の意図がうまく伝わらないのは、どこに原因があるのか?」と問い直すクセを身につけたところ、会議の進め方や資料の作り方に変化が現れ、社員との連携が見違えるほどスムーズになりました。サラリーマンは、ある意味「ミスを恐れる」ことが仕事の一部です。
昇格や評価がかかっているため、失敗しないことが重視されます。
一方、経営者は違います。ミスは避けられない前提で、いかにリカバリーするか、どう再発を防ぐかが問われるのです。つまり、ミスが起きたときに「誰が悪いか」ではなく、「次にどう備えるか」を思考することが、成長し続ける経営者の条件です。
ここでひとつ、自責思考を養うための習慣をご紹介します。それは、「今日あった違和感を3つ書き出す」こと。
(例)
・なぜ、あのとき言葉が詰まったのか?
・なぜ、あの社員は不機嫌に見えたのか?
・なぜ、自分はあの場面で不安を感じたのか?
これらを「相手が悪い」で済ませるのではなく、「自分にできたことはなかったか?」
という問いを添えて書き出すことで、次回に備える視点が磨かれていきます。
違和感を感じた時は自分の感情が何かしら動いた時。その場では難しくても、文字にして書き出すことで客観視することができ、思考の深みが増します。
経営の現場は、ミスをゼロにする世界ではありません。むしろ、ミスからどれだけ学び、次に活かせるかが勝負。「すべての原因は自分の中にある」と言うと、少し重たく聞こえるかもしれません。でもこれは、他人に振り回されず、自分で経営をコントロールするという自由への第一歩でもあります。経営者にとって最も重要なのは、結果を他人のせいにせず、次の一手を自らの意思で決められる力。そしてその根っこにあるのが、「自分にできることは何だったかを問い直す」という意味での「自責思考」なのです』(知恵の和ノート 第584話より)◆◆◆
まさにこの自責思考こそが企業組織の根底になければいけないはずだ。
しかし、組織の管理手法として減点主義がある以上、他責思考に陥りやすい。他責思考にすることで自己の精神的安定性は保たれるし、減点評価も逃れられる。
しかも、リスクをとるという思考は排除されるから、自己の業務範囲も縮小傾向になりやすい。
この組織からはイノベーションは起こらないし、ボトムアップの組織にはならない。
企業経営者の最大の課題は自分を含め、社員を他責思考から自責思考へと持っていくことだ。
当社でもミスやクレームの大部分は社員の他責思考が原因となっているが、当の本人にはその自覚はない。
直近の例を挙げると、自動火災報知設備の点検がある。
管理会社としては定期的に点検し所轄の消防署に報告する義務がある。
30日前に入居者に立ち合いと入室の許可を得ることになっているが、中々返事がない事が多い。
再度7日前に都合の良い日を打診するが、なしのつぶてのケースもある。
入居当初の賃貸契約書でも立ち合い義務と入室許可をもらい、放置した場合の損害賠償責任を課す条項もあるが、実際には立ち会っていただいている。勿論不在の場合の入室許可も得ている。
今回のケースは、入居者との入室予定日が担当者との事務社員の間で3日前の変更依頼が伝わっていなかったケースだ。
結果的に不在にかかわらず入室したことになり、入居者から損害賠償請求をされたのだ。
当事者からすれば間に休みがあったこともあり、その入居者からの連絡が担当者ではなく事務社員の受信したメールだった為、その確認が遅れた。結果的に担当者には連絡がなく、そのまま点検を実施したわけだ。そこには事務社員の同僚も在籍していたが、担当者が休暇で不在にもかかわらずそのメールを確認しなかったのは、「それは自分の範囲外で」その義務はないし、連絡も不要と主張した。入居者から見れば社内の担当分けなど関係がない。
理由にならない理由を言っても社会常識から言っても通用しないが、社内ではそれが平然と通じる感覚がある。
企業体制はある意味効率化を目指すものだが、リレー部分をきちんと接続しないとかえってミスや非効率につながってしまう。相補関係が必要で、そこに部門リーダーの川上、川下への配慮如何で決まってしまう。仕事は他人に渡して終わりではなく、相手がその内容を理解して初めて完結するものだ。業務のスキマは、多人数が関与する中では必然的に起こることであり、この辺りのカバー役が自責思考を持った社員である。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之