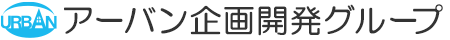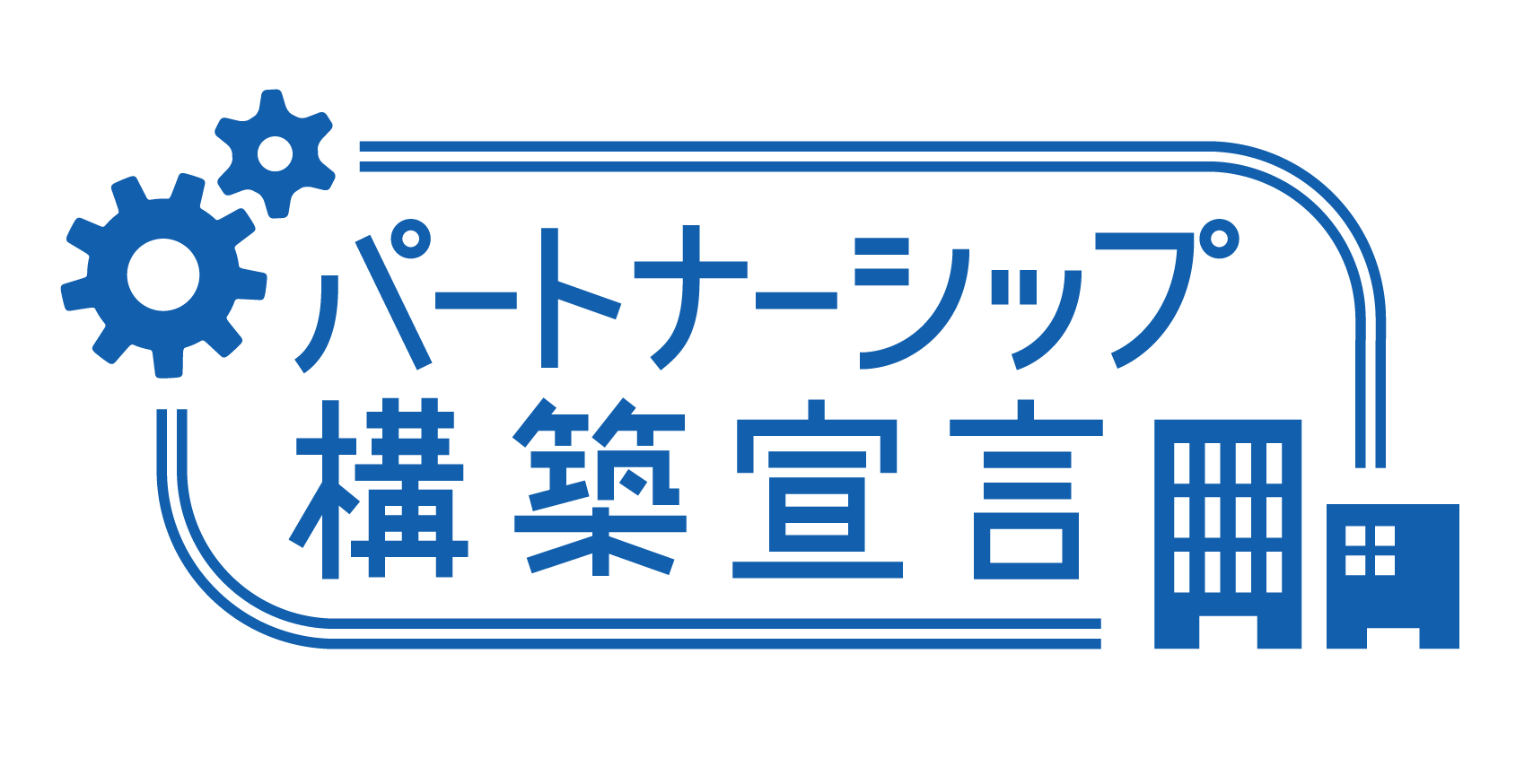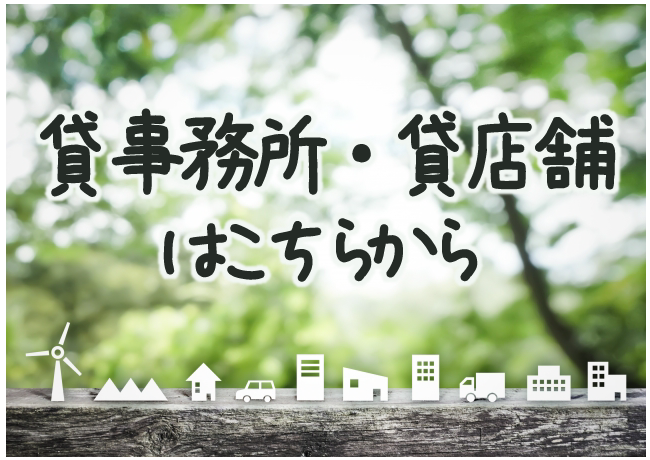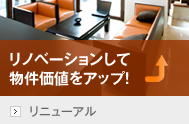[ 2025.9.1. ]
336号-2025.9
 マーケティング業界で誰でも知っている有名な逸話を2例挙げてみよう。
マーケティング業界で誰でも知っている有名な逸話を2例挙げてみよう。
その一つは、人が来なかった動物園が日本一になった話。それは...北海道 旭川市にある旭山動物園のことだ。年間3億円の赤字を出すようになり「市のお荷物」とされ閉園に追い込まれた動物園をV字回復で黒字化させたのは、以前は「飼育係長」を務めていた一人の新園長だった。1996年に園長に着任した小菅 正夫(こすげ まさお)氏は顧客視点のマーケティングを取り入れ、「ある重要な事実に気づき」再建の糸口を見つけた。小菅氏は顧客の視点で動物園を見てまわり、驚いたそうだ。「動物たちがみんな来園者にお尻を向けているではないか…」本来は、動物の躍動感やリアルの動物と対峙する緊張感を感じてもらうための動物園のはずだ。しかし肝心の動物たちは来園者に向くどころか、まるでテレビでも見ているかのような丸まった背中を向けていた。それもそのはずだ。動物たちにとって注意を向けなければいけない「エサを運ぶ、飼育係」「注射を打つ、獣医師」はみな裏側から出てくるからだ。つまり動物たちがイキイキとした表情や緊張感を持った表情を向けるのはすべて裏側だった。動物たちにとって来園者の方向を向く理由がない。
そこで小菅氏は動物へのエサやお世話を「来園者側から」行うように飼育方針を変えた。
さらに来園者や現場の飼育係たちからも声を集めたそうだ。すると来園者からは「この動物たちは檻の中で 自由がなくてかわいそう」という声が上がり、飼育係から「もっと活き活きと動き回る動物たちの姿を見せたい」という声が上がる。これらの意見を形にするため小菅氏は旭川市に対して「行動展示」という企画を立案した。結果、「1億円」の追加予算を獲得することに成功する。そして旭山動物園は生まれ変わった。低迷していた来園者数は上野動物園を上回り「来場者数日本一の動物園」になった。人気は落ちることなく現在も国内5本の指に入り年間100万人以上が来園する人気パークになっている。この大躍進のきっかけは、まぎれもなく経営者が「顧客視点」を持ち「組織の強み」を活かすことにある。この定番の「顧客志向」「顧客目線」がマーケティングの基本だが、組織の中で定着させることは難しい。企業存続を唯一の命題とする企業トップの役目はこの定着化にある。顧客目線でものを考えなければ企業の存続は難しい。更に大事なのは「現場主義」という動きだ。往々にして忘れがちになるのは、この現場主義だ。三現主義ともいう。実際に現場で現物を観察し、現実を認識したうえで問題解決を図らなければならないという事になる。意外と担当者の報告を鵜呑みにして判断を下すことが多く見受けられる。担当者からの報告はバイアスがかかることが多く、報告内容に疑問点や不明点があれば労をいとわず、自ら現場に出向き自分の目で判断することが必要だ。これをしないとトラブルや苦情が解決不能なほどに発展してしまう事がある。当社でもそれを怠ったために、払う必要もなかった賠償金が発生したこともあった。
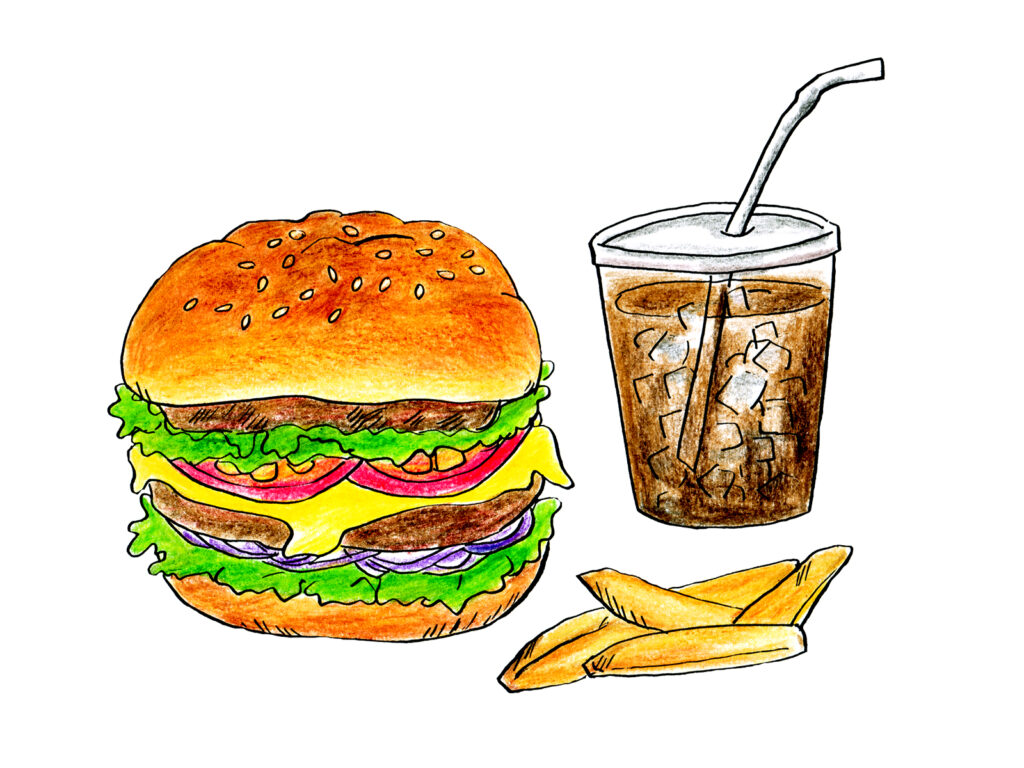 もう一つは、飲料のドクターペッパーの話だ。
もう一つは、飲料のドクターペッパーの話だ。
遠くない未来に飲食業界のガリバーであるコカ・コーラがドクターペッパーに負ける日が来るかもしれない。独特なフレーバーと個性的な味で魅了するドクターペッパーは、杏仁豆腐のような味わいで日本でも「変わった飲み物」として認識されていた。一時期は「マズイ」「ハンバーガーと一緒に飲むものではない」という評判もあったが、今、海外の若者の間でドクターペッパーが大ヒットしているという。ただし日本国内ではいまひとつヒットはしていない。
米国ではスプライト、ペプシ、ジンジャーエール、ダイエットコークなど全ての競合を撃破しコカ・コーラに次ぐシェア第2位まで上り詰めた。日本では1885年誕生のドクターペッパーは、コカ・コーラ社が販売しているが、アメリカでは製造元のキューリグ社が販売しているので競合先といえる。製造して130年もの長きにわたって消費者に支持されているのは驚異的であり、米国人の必要不可欠な飲み物になっている。急成長の秘密はあのコカ・コーラも白旗を振ったマーケティングにあったと言われている。
ドクターペッパーは一体どうやって若者の心を掴みコカ・コーラの脅威となったのか?
成功の秘訣を一言で言えば「コカ・コーラとは戦わない」という「独自のポジション」を築いた結果だと分析されている。
「コカ・コーラが脅威なのに戦わない!ってどういうこと?」と不思議に思うかもしれないが、実は、日本とアメリカではコカ・コーラを飲むシーンが違うという事だ。
日本では「のどが渇いた時」「休んでいる時」「お風呂上り」などだが、アメリカでは「食事の際に飲む」というのが主流になっている。その主流に合わせるためコカ・コーラは「すっきりとした味わい」になっている。日本人からすると甘く感じるが、アメリカでは甘くない部類に入るらしい。ドクターペッパーはそこに目を付けた。「食事以外のシーンでならコカ・コーラと戦わずに売れるのでは?」ドクターペッパーは甘味たっぷりのフレーバーでコカ・コーラ以上に甘い商品だ。食事の際の「飲み物」ではなく若者に「おやつ」として楽しんでもらおう!と考え戦略を立てた。
・ココナッツ、ストロベリーなどおやつを好む若い女性向けの商品を開発
・若者が通う飲食店のドリンクバーに設置など。
この戦略が大ヒット!長年コカ・コーラと戦ってきたペプシも抜き、全米2位のシェアになった。コカ・コーラを脅かすほどシェアを広げることに成功した。このように競合と競わない「利用シーン」を見つけることで飛躍的に売上を伸ばすことが出来る!
今はやりの言葉で表現するなら、ブルーオーシャン戦略(従来存在しなかった新しい市場を生み出すことで、新領域に事業を展開していく戦略。未開拓かつ競合のいない市場を、青く輝く穏やかな海に例えている)という事になる。
ここで考えるべき、お客さまから喜ばれる「独自の利用シーン」とは一体何なんだ!という事になる。これさえ見つけることが出来ればどんな競合がいても、お金が無くてもどんどん集客できるようになりお客さまに困ることがなくなるはずだ。今ある商品から独自のシーンを見つけるためには
・お客さまがどんな人で
・何を考えていて
・何に興味を持つのか
・そのお客様にとっての利便さ
を考えることだが、サービス業を担当するものである以上、この視点は全員が必要条件となる。常に顧客サイドの思考で価値を提供する企業こそ顧客に愛され頼りにされる企業といえる。どこよりも早く、正確に、正当な価値を提供できる企業こそ存続を許される企業になれると心すべきである。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之