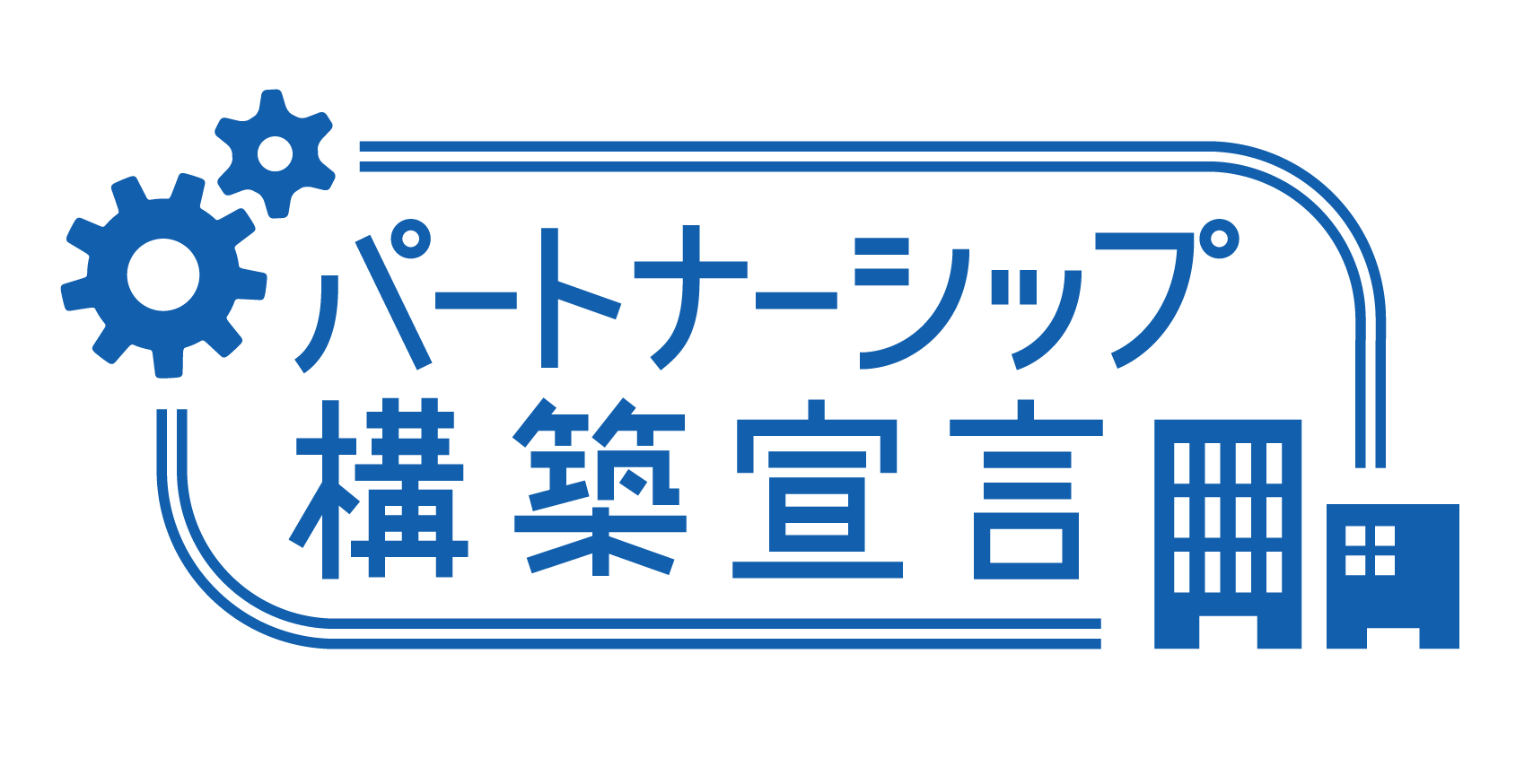[ 2015.9.25. ]
218号-2015.9.25
 淡路島ぐらいの広さの国土しかない貧しい小国が、今や1人あたりのGDPは日本を上回る世界有数の富裕国となった。日本経済新聞『私の履歴書』(1999年1月分)に登場したリー・クアンユー回顧録[上]では原爆投下については「広島と長崎に原子爆弾が落とされなければ、数十万人に上るマレーとシンガポールの民間人や、日本人でさえも数百万人が犠牲になっていただろう」と述べている。1994年に「つばを吐いたり、ガムを噛んだり、ハトに餌付けをしたりした」300万人のシンガポール市民を罰することの効果についての30年間の研究に対して」との名目で、イグノーベル賞心理学賞を授与された。評価については毀誉褒貶もあるが、間違いなく「アジアの時代」を作った「シンガポール建国の父」の名誉は揺るがない。「シンガポールに住んでいる米国人少年が車に赤いスプレーで落書きしただけで鞭打ちの刑」「国内でチューインガムの販売禁止」「ゴミを捨てただけで罰金」などなど、ヒットラーなどの独裁者と同じ恐怖政治とも言うべき強権発動の数々もあった。
淡路島ぐらいの広さの国土しかない貧しい小国が、今や1人あたりのGDPは日本を上回る世界有数の富裕国となった。日本経済新聞『私の履歴書』(1999年1月分)に登場したリー・クアンユー回顧録[上]では原爆投下については「広島と長崎に原子爆弾が落とされなければ、数十万人に上るマレーとシンガポールの民間人や、日本人でさえも数百万人が犠牲になっていただろう」と述べている。1994年に「つばを吐いたり、ガムを噛んだり、ハトに餌付けをしたりした」300万人のシンガポール市民を罰することの効果についての30年間の研究に対して」との名目で、イグノーベル賞心理学賞を授与された。評価については毀誉褒貶もあるが、間違いなく「アジアの時代」を作った「シンガポール建国の父」の名誉は揺るがない。「シンガポールに住んでいる米国人少年が車に赤いスプレーで落書きしただけで鞭打ちの刑」「国内でチューインガムの販売禁止」「ゴミを捨てただけで罰金」などなど、ヒットラーなどの独裁者と同じ恐怖政治とも言うべき強権発動の数々もあった。
最近では夜の10時30分から朝の7時まで公共の場での飲酒と、小売店でのアルコール類の販売が出来なくなり、その厳しさは今でも顕在だ。「国家の発展には民主主義よりも規律が必要」というリー氏の信念に基づく強権政治は欧米からもかなり強く批判された。
例えば、上記の米国人少年の鞭打ちのときはクリントン大統領がシンガポールに経済制裁をしようとまでして圧力をかけた。しかしリー氏は断固としてその方針をやめようとせず、その姿勢がかなりの部分で正しかったことが50年間のシンガポールの歴史が証明している。
振り返ってわが日本国を見ても、相手のレベルが低いうちは、トップダウンの強権政治の方が良いことが多い!!と思うことがある。民主政治は《愚民政治》の危険性が内在し、最悪の制度といわれるが、現時点でこれに過ぎる政治制度もないことも事実である。
反論もあると思うが民主主義と称して、国民一人一人の意見なんか聞いたって、50年前のシンガポールではろくな意見は出なかったのではないかとも思う。小学1年生に対して、会社の方針について意見を求めてもろくな意見が出ないのと同じで、この「相手のレベルが低いうちは、ある程度強制的に従わせるようなリーダーシップが必要」かもしれない。今の学校教育を見ても、教師と生徒が平等の立場にあるはずがない。戦後教師を聖職から労働者の立場にさせたのも、日教組をはじめとする「民主教育改革」であった。徒競走で全員が手をつないでゴールしなくてはならないのは、競争(差がつく)を全て悪と見た結果である。
会社でも同じことが起きている。「ブラック企業」のイメージが歪曲されて報道され、22歳にもなった自分の子供に、入社の判定を親がし、問題がなければ入社の承諾をするらしい。だから、採用側は入社希望の受験生より親にいかに好印象を与えるかに腐心している。又其の親は残業や勤務内容まで口を挟み、人事担当者の主要な折衝業務の一つにもなっている。
選挙権も18歳に引き下げることになった。世界の趨勢というけれども、それだけの社会教育もせず、社会常識にも首をかしげる多くの若者の存在がある。外見上は体格も立派だし、話さない限り其の内面性も問題がないように見える。
しかし政治にも経済にも無関心で無知に等しい若者に国家の行く末をストレートに託すのはどうかと首をかしげる。欧米の個人主義的価値観を戦後の日本は積極的に受け入れてきた。しかし、個人の権利と表裏をなす「社会の責任」に目を向けられないまま、個人の片面だけが浸透した。他人の目を気にする事で自己を律するという伝統的な規範の形を失い、一方で社会的責任を伴う個人主義を確立した訳でもない。そこに倫理不在の状況が現出している。
人様が見ているという親の世代の価値観を「古い」と拒み、バラバラな社会を招いてしまった責任は私たち団塊の世代にある。この世代が、今企業社会から地域社会へと活動の場を移そうとしている。社会が私的領域だけで成り立っているのではない事にやっと気付いた我々には後続世代に伝えていく責任があるわけだが、其の勇気も時間もないのが実情だ。まして様々な改革施策が自分の老後に影響するとすれば尚更だ。勿論、これは若者の分母を増やし、高齢者の投票行動によるバイヤスを是正し、高齢者優遇措置を緩和させ負担を増加する政策手段である点は間違いがない。かっての制限選挙に戻すというのは暴論ではあるが、シンガポールのリー氏率いる人民行動党が国会の議席の過半数を独占し、世襲制に近い形で、長男のシェンロン氏が首相就任した。他の自由を標榜する国家でも同じような政治形態をとる国家も多い。つまり、結果として「国民の幸福につながる」なら政治形態は問題にならないということになる。
会社という組織でも同じことが言える。
事業承継を含む世襲制の問題だ。
「一個人の力量に頼っているだけの国家の命は短い。何故なら才能が如何に優れていようともその人の命が絶えれば全てが終わりだからである。しかも先の指導者の才能が後継者に受け継がれるというのは実にまれな例であるのだ」マキャベリ(ローマ史論)
かって世襲制が日本の経営の癌のように言われた時期があった。株主重視の風潮がそれを後押ししたが、長期的な視野にたった経営ができないとの理由や、トヨタのように世界的優良企業が創業家により経営が見直されていることもある。創業家がトップに立つからではなく、偶々選ばれたトップが創業家出身だったのに過ぎない。長年をかけて「後継者を育てる」と豪語した社長に限ってその後継者が冴えないケースが多い。国家も同じで、スターリンも毛沢東も後継者の育成と指名で悩み続けた。
死ぬまで悩んだ結果の後継者が、彼らの死後に必ず短命で終わる。本物のリーダーにとって代わられるからだ。名経営者が選んだ経営者はほとんど期待はずれで、天才指導者が育てた後継者はほとんど権力の頂点に留まれないといわれる(世襲は例外)。それは本物のリーダーが選ばれるものではなく、混乱や困難を通じて生まれるものだからだ。民主主義になったからといってこの原則が動揺するものではない。日本の政治をみれば一目瞭然だ。5年間で7人もリーダーを選んだが、本物のリーダーが出現しただろうか?
企業経営者の悩みの一つはこの後継者選びだ。昔のような帝王学を納めさせる時間もないし、社会状況は激変しておりモデルにならない。そこで出てきたのが「経営理念」という考え方だ。この企業のDNAを軸に沿えれば、判断基準の元になり企業の方向性はぶれない。経営理念をいかに浸透させるかは企業トップの責任になるが、夫々の職掌範囲が明確になり組織が旨く回転するようになる。リーダーの役目はこの理念をいかに解釈し組織に浸透させる事だ。
そして企業トップの重要な仕事の一つが、「決断」である。決断は責任を負うことであり、責任を負うとは会社をつぶさないことでもある。
それが当社の「厳しいけれど楽しい会社」を目指す近道になる。
社長 三戸部 啓之