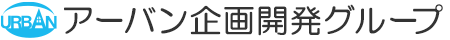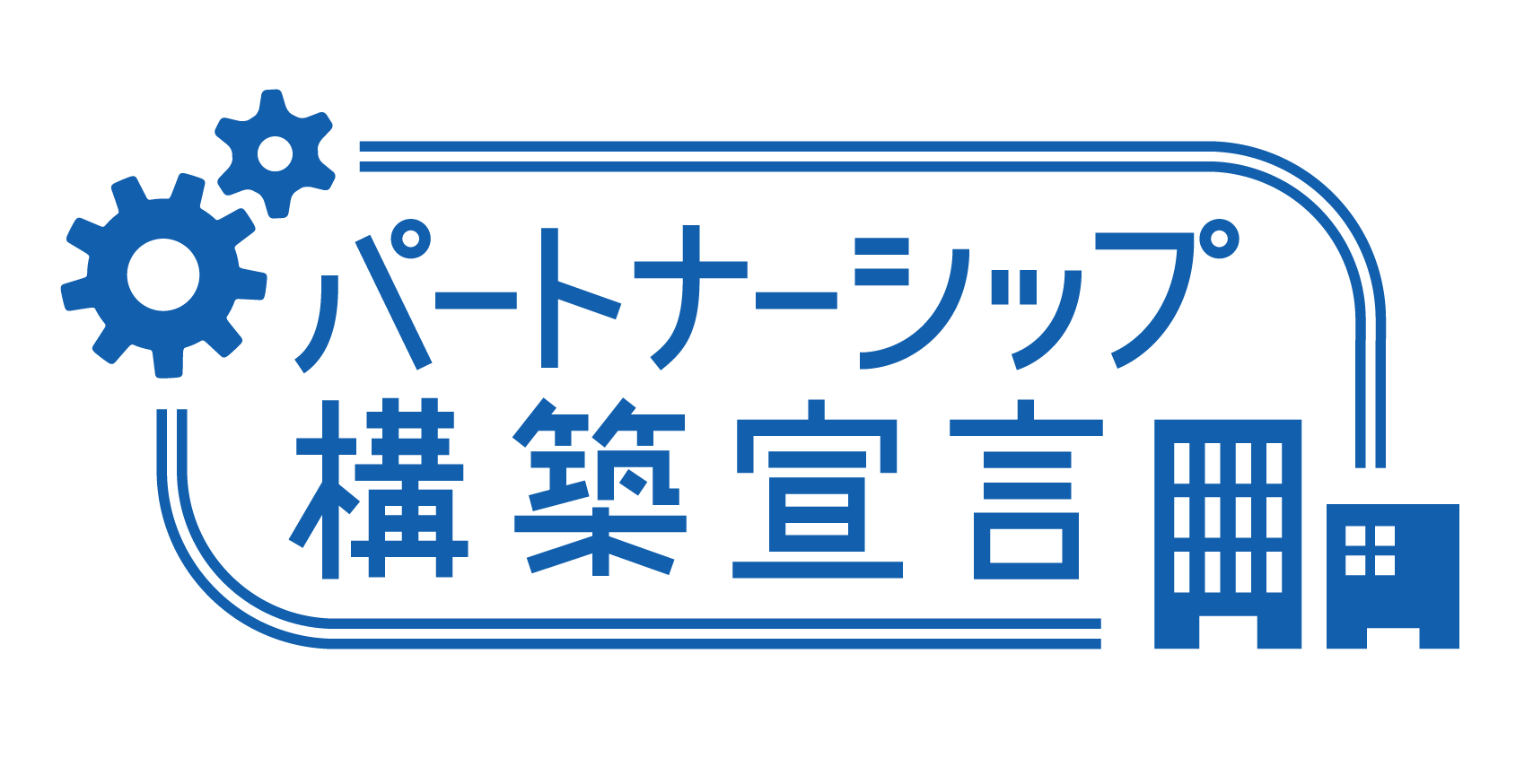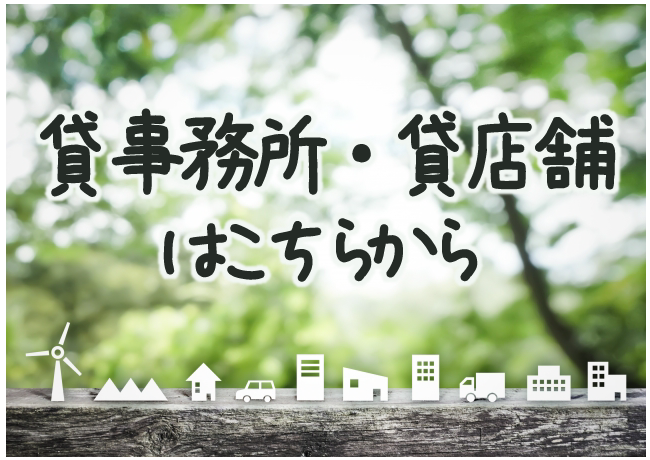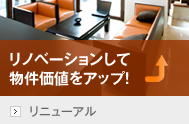[ 2025.8.1. ]
335号-2025.8
 ミュージシャンの矢沢永吉さんがイベントで地方を回っている時の話がある。ある時、スタッフの手違いで矢沢さん用のスイートルームを予約できていなかった。 このことをスタッフが恐る恐る矢沢さんに伝えたときの返事が、「いいよ、部屋がない訳じゃないんだから、気にしないでよ!」と言った直後に、「ただ、俺はいいけど、YAZAWAが何て言うかな?」この後、すぐにスイートルームが用意された。「ロックスター・YAZAWA」とは、彼が成り上がっていく中で、彼自身が作り上げた性格またはファンがこうであって欲しいと思い込んでいる理想像なのだと理解できる。
ミュージシャンの矢沢永吉さんがイベントで地方を回っている時の話がある。ある時、スタッフの手違いで矢沢さん用のスイートルームを予約できていなかった。 このことをスタッフが恐る恐る矢沢さんに伝えたときの返事が、「いいよ、部屋がない訳じゃないんだから、気にしないでよ!」と言った直後に、「ただ、俺はいいけど、YAZAWAが何て言うかな?」この後、すぐにスイートルームが用意された。「ロックスター・YAZAWA」とは、彼が成り上がっていく中で、彼自身が作り上げた性格またはファンがこうであって欲しいと思い込んでいる理想像なのだと理解できる。
つまり矢沢永吉さんはYAZAWAを命がけで演じているということになる。
「1人の人間としての矢沢永吉はスイートルームじゃなくても 別に問題ない」
「でもロックスターとして走り続けるYAZAWAのイメージを崩してしまわないかどうか、ファンの期待を裏切ることにならないか今一度考えてみて欲しい」という言葉は、決して成り上がった人間の見栄や我儘からではなく、自分が演じているYAZAWAを守ることを徹底していることから自然に出た発言なのだと思う。それは矢沢永吉の生きざまを理解しているからこそ言える言葉だ。
「ファンから期待されている自分を、全力で演じ続けられるってなんてカッコいいんだろ!」と思ってしまう人はたくさんいるはずだ。勿論、その裏付けには常人が予想もつかない努力があるはずだが・・・
人にもよるが、前段の「いいよ、部屋がない訳じゃないんだから、気にしないでよ!」で終わることも多い。
しかし、気の利くお付きの人は「ただ、俺はいいけど、YAZAWAが何て言うかな?」まで考えて行動を起こすという事だ。ここまで気が付くお付きがいれば隅から隅までの気配りができ、相手のブランドを維持する事ができるだろう。人の二歩三歩先を見て動ける社員がいれば社長の評価や会社は安泰だろう。
業績のいい企業には必ずこういう社員が一人はいるものだ。当社にも有難いことに居る。
教育で何とかなるものではない、隠れた素質を見つけるのも社長の眼力といえるだろう。
こんなことを書くとコーチングやカウンセラーの人から「そんな本来の自分をある意味押し殺して、周りの人間の期待に無理に答えようとしなくても良いのでは?」なんてご意見も言われそうな気がする。
やっぱりその生き方の方が何倍もカッコいいし、夢があるし、自分もそうありたいなぁ~と心の底から思う。
このように、真剣に自分の作ったキャラを演じ抜く!格好いいけれどそれを継続し、徹底するのは数倍難しい。下手をすると、単なる「虚勢を張っている!」と評価される不利益もある。「ヤザワ」だからできる事で、そのまま一般人がマネをすればいっぺんに反感を買う事間違いがない。それができるには、それなりの実力と評価が裏付けなければならない。そこを勘違いすると「単なる成り上がりもの」「偉ぶっている嫌味な奴」との評価は甘受しなくてはならない。
かつて、役者は役に徹したイメージを壊さない事を身上としていた。ある有名な俳優は、出演のオファーがあっても自分の役者イメージを壊す役にはどんな高額なギャラでも承諾しなかったし、プライベートでも役者のイメージが壊れることを気にしていた。それがプロというものだろう。それが役者矜持といえる。そこには自制というものがきちんと機能していた。勿論所属事務所からの規制もあったはずだが、イメージという財産を大事にしていた。イメージには社会的寿命というものがあり、時代の要請に合わなければ役者の寿命も尽きたことになる。イメージ転換を図る役者もいたがその成功例は少ない。それほど視聴者に根付いたイメージを変えることは難しい。
数少ない例として「高倉健」がいる。1960年代から1970年代にかけて、任侠ヤクザ路線で一世を風靡した稀代の名優だが、「義理と人情に厚く寡黙ながらも強い意志を持つ男」というイメージが定着していた。
1976年に東映を退社しフリーとなった事で任侠映画から離れ、より人間ドラマに焦点を当てた作品に出演するようになり、「八甲田山1977年」「幸福の黄色いハンカチ1977年」は彼のイメージを変えた作品の一つと言われている。その後も「鉄道員1999年」等の作品で寡黙ながら温かみのある人物を演じ、彼の演技の幅を広げた。高倉健のイメージチェンジは、単なるジャンルの変更ではなく彼自身の演技スタイルの深化であった。
ビジネス社会でも、「社長らしく」がある。業種別でもヤクザらしく、銀行家らしく、芸術家らしく等一般社会で巷間されているイメージがある。最近ではそのイメージを払底するような風体の人間が多くなったが、マダマダその利便性や効果もあって生きながられている。
 バブル期には社長の3条件というものもあった。金縁のローレックスの腕時計、洋服はアルマーニ、ライターはデュポン、車はベンツだった。これに喜平の金のネックレスが付け、サングラスをかければヤクザそのものだ。今なら噴飯ものだが、その時代には何の抵抗もなく一般人が取り入れていたし、特に不動産業界では定番商品だった。
バブル期には社長の3条件というものもあった。金縁のローレックスの腕時計、洋服はアルマーニ、ライターはデュポン、車はベンツだった。これに喜平の金のネックレスが付け、サングラスをかければヤクザそのものだ。今なら噴飯ものだが、その時代には何の抵抗もなく一般人が取り入れていたし、特に不動産業界では定番商品だった。
ある時、不動産の契約時に私は使い慣れている100円ボールペンでサインしようとしたら、相手の業者から「あなたは数千万の不動産物件の契約にその筆記用具は相手に失礼ではないか!」と指摘された事がある。その方が言うには、せめて万年筆ならシェーファーかモンブランを使うべきだという。ボールペンなら最低クロスだという。ここで筆記用具のいわれを滔々というのも可笑しいので、その方のボールペン(メーカーは忘れたが)を借りてサインしたことがある。つまり売買仲介という高額商品を扱う以上、筆記用具もそれなりの高価なものを使え!という訳だ。不動産だけでなくある外車ディーラーの営業マンに言われたこともある。曰く、高級外車を買う顧客はそれなりの身分の方なので、会社でも持ち物や服装もブランド品でキチンとそろえなくてはならない決まりがあると言っていた。勿論今はそんなこともないと思うが、当時はそれが一つのルールでもあったようだ。
外見から判断されるという意味では、氏素性を説明する必要もない。人は見た目で判断されるからだ。
その違いがあれば、説明に及べばいいので当の本人には楽になる。そこに新たなコミュニケーションツールができるわけだ。特に初めての顧客に接する場合には、第一印象次第で結果に影響が出る。
そういう理由から、社内教育でも、挨拶や座り方、話し方、聞き方の基本動作を教育する。相手に好感を持ってもらう仕草がポイントになる。馴れ馴れしいと親しいを勘違いする社員もいる。
当社の経営理念である「顧客の最良のパートナーになる!」には、先ずは外見からになる。
基本動作の指導を新人研修で行うが、一部の社員からまさにブラック企業ではないか!という苦情が出たことがある。最近は自分に都合の悪い事や、面倒なこと、強制されることは全てブラックという表現で自己正当化を図る風潮がある。しかも早期に結果を求める風潮があるので、将来を見据えた自己改善など初めからネグレクトしてしまう。「成らぬ堪忍するが堪忍」「雨垂れ石を穿つ」などが修行の身では当たり前だったが、最近ではこの言葉もトンと聞かなくなった。この熟語も若い人にはなじまない言葉だろうから、コメントをしておくと、前者は「我慢できないことをこそ我慢するのが本当の忍耐である」という意味であり、後者は「小さな努力でも続ければ大きな成果を生む」という意味になる。努力や苦労に価値観を置かない社会は、何れ金権投機的な物質至上主義社会になってしまう。モノの所有が唯一の差別化要因になってしまい、このままでは我が日本も危うくなりそうだと危機感を持っているのは、団塊の世代である後期高齢者に足を踏み入れた「ジジイ」だけなのは、返す返すも残念だ。
アーバン企画開発グループ相談役/合同会社ゆいまーる代表社員
三戸部 啓之